|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
 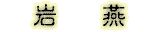
那須朝日岳遭難追悼号 |
高松さんと僕(丹沢での一日)(1972) |
| 僕らは、近くの山々を、じっと見つめながら、お互いにしゃべった。高松さんは、いろんな事を語ってくれた。
「夏合宿は、こんなもんじゃないよ。」 高松さんは、そういって、うなずくと、 「ヘヘッ俺は、弱いからな。」 と言った。僕は、その時、ほんとうに、おどろいたのだった。山に登る、その、きびしさと、泣いても登って行く高松さんに、おどろいたのだった。僕の頭には、次のような、場面が、なまなましく、描き出された。 山道が、ずっと高い山まで続いている。周囲は、やはり山ばかりである。そこに、一つのパーティーが、やってくる。だけど一人が、たおれそうだ。ふらふらしている。 必死に歩いている。だが、ついに、その人は地面に、座り泣き出すのである。 「ちくしょう!ちくしょう!」 彼は、歯をくいしぱるのだけど、目からは大きな泪が、ポトポト落ちて行く。 そして、又、歩くのである。 人間が、"真に、生きる" とは、こういう必死になってガンバル姿を言うのではないかとも思った。 「お前なんで、山に登る気なんかになったの。」 高松さんは、僕に聞いた。 「うーん、別に、これという理由は、ないけど、なんとなく、高松さんは?」 まるで、てれるように、そう言った。 「おかしくなんかないよ。」 僕は、むっとなって言った。なぜか、おかしくないんだ。とんでもない。僕はその時始めて高松さんを、見たような気がしてきたのであった。 「俺っておかしいな。」 おなじ問答をくり返した。僕は、高松さんの顔をそっとのぞいてみた。なぜだかわからないけれど、あまり純粋すぎる、と思った。 同時に、そうした純粋な心を、うらやましく思った。 「俺ってよう、今は、こんな、不まじめだけど昔は、けっこうまじめだったんだぜ。」 突然こんなことも、言い出した。僕には、そのことはが、あたかも、こう言っているように聞えた。 「俺は一見ふしだらなやつだが、俺ほど、マジメなやつは、いないぜ。」 だから僕は、こう言った。 「今でも、けっこうまじめなんじゃないの。」 すると、高松さんは、フフッと笑って 「いや、ふまじめさ。」 と言った。 しばらくして僕らはそこを降りた。 下りは、あまり、いいながめじゃなかった。とにかく、暑かったし、急な坂ぱかりであった。 突然、高松さんは、そこで、大きな声をはりあげてうたい出した。ものすごい、バカでかい声で。 まわりの人達を、無視して、歌詞を思いつくかぎり歌うのである。 僕にも歌えと言った。だから大声で、僕も歌った。また逢う日までからヘイジユードまで、だけど、だけど、どっかにつっかえるものが、僕には、あった。 高松さんの歌う声と、僕のはり上げる声はぴったりと合うことは、なかった。 |
僕は、高松さんが死んだという知らせを聞いた時、先ずそれを絶対に信じなかった。 だって、彼が死ぬはずがないのである。彼がもし死んでしまうのだとしたら、それは、おそらく、エベレストであり、マナスルであり、マッターホルンである。 しかし、こうして、月日が経ち、高松さんのことを考えると、彼が死んでしまってもういない、という事実がやっと納得できるようになった。 高松さんは、僕に、あまりに多くの事を教えてくれた。それは、彼が、口で説いた教えではなく、実際に、高松さん自身の行動で示してくれたのだ。 必死に、生きようとした、彼のなまなましい生活が僕には、うらやましい。 テストや成績なんか、ちっとも気にしない固い自信が、僕には、うらやましい。 彼がもし、この "山" という道を選ぶ前に、おそろしい不運がこの道の上にまちかまえているという事を知っていたとしても、高松さんは、今歩いてきた道をもう一度歩いていただろう。歩いていたと信じる。 そして今、どこにもいない今も、決して、後悔していないだろう。いやしていない。していないと信じたいのだ。 僕は、死んだ人間が、生きていた時、ああであれぱ、こうであれば、などという話をしたくもなけれぱ、聞きたくもない。 高松さんが、17 年間に、生きた、力あふれる生活を、僕らは、決して、無駄にしてはいけない。 僕は、高松さんが永遠にこの世で生き続けるということを可能にする方法を知っている。 それは、僕の心の中であり、高松さんを愛する人の心の中である。 高松さんを生かす方法は、たったひとつ。高松さんの思い出を語るのでもなく、くやむことでもない。それは、僕らが確実に生きることである。真に生きて行くことである。 僕らが生きて行くことによってのみ、高松さんは、僕らの心の中で、生き続けることができる、と信じてうたがわない。(山岳部員) |
| home > history > iwatsubame > nasu 72 >高松さんと僕 | ||
(C) 2000-2026, azabu alpine club
text by a. "gataro" watanabe
all rights reserved.
| ホーム || これまでの活動 || ギャラリー || コラム || 山岳部員・OB会員のページ || 掲示板 || このサイトについて |
| 岩燕メイン || I-V号 || VI-IX号 || 那須追悼号 || 岩燕総合インデックス || 管理者へメール |

