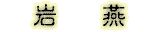|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
tome V
山の明暗(1958)風間昌司(部長 1955-1957)
|
大正五年七月下旬、寮生約三十名と富士に登った。中学に入って初めての夏休みであった。大宮、今の富士宮の旅館に一泊し、夜の明けないうちに身仕度して出発した。不要の持物は一切そのまま御殿場の宿屋に回送される仕組みになっていた。
頂上では、余程運がよかったと見えて、雲海の遥か彼方に天龍川の上流が見えた。房総半島から東海地方の海岸線も、霞がかつてはいたが、その輪廓を示していた。この素晴らしい景観は三十数年を経た今でも瞼に浮んで来る。今日では、殆ど誰もが、何処へ行くにもカメラをさげて行くので、貴い印象はカメラ任せで、自分の目に映じ皮膚に感じる実感は、カメラを持っているだけに、却って幾分うすらいで来ているのではなかろうか。十枚の写真より心に映じだ一つの感銘の方が貴い気がする。もう一つ忘れないことがある。麓から眺めた富士を見て、もう富士はわかったという人があれば、その人は嘘つきだということである。これは終生の教訓になつた。大宮口で眺めた富士はすっきりと青く澄んでいた。頂上は赤さびた大小の石がごろごろしていて、夢の様に楽しい憩の場でも何でもなかった。それでも、流石に自分の足で、日本の、一番高い地点、三七七六米の高さに達したんだと思った時には、友達同志で肩を組みながら、何やらわけのわからぬことを叫んだ様におぽえている。今日の「やあつ、ほう」の類だったろうか。この歓びは、やがて金剛杖の先端に自分の汗に濡れた手拭を結びつけて、それた石ころの上に立てさせたのであった。その旗は冷たい風になびいて、ひたひたと音を立てた。 一九五四年エヴェレスト山頂に旗を立てたヒラリー氏の姿を映した映画の一こまに接したとき僕は涙が出た。一九五六年マナスルの頂上に立てーた日の丸の旗は、鋭い風にばりばりと音を立てたことだろうと思う。 |
何時間経つたかわからないが、不図目をさました。身体がなまあたたかい。太陽が照っているのだった。起ち上ると、すたすたと歩ける。道に出ると、村の子供に行き遭った。その少年を見るや否や、途端に空腹をおぽえて言った。 「おい、ぼうや、この辺にまんじゆう屋はないか」 この言葉には切実な実感がある。疲労で身体が甘さを要求している。元来、まんじゆうという菓子は、密度が高く充実感があり、すぐに口に入れられるという便利がある。その少年は敗残兵の様な弟を見て、幽霊と間違えたか、一散に跳び去って行った。やがて、或村人の家で食事を与えられ、人心地がつくと直ぐ友人の事が気になつた。早速村人を伴って探査に向った。何時間か懸って友人は見つかつたが、弟の人工呼吸も遂に効をせせず[ママ]、友は遂に帰らぬ客となってしまったのである。 |
|
| home > history > iwatsubame > I-V > 山の明暗 | ||
(C) 2000-2026, azabu alpine club
text by m.kazama, photo by n.takano. all rights reserved.
| ホーム || これまでの活動 || ギャラリー || コラム || 山岳部員・OB会員のページ || 掲示板 || このサイトについて |
| 岩燕メイン || I-V号 || VI-IX号 || 那須追悼号 || 岩燕総合インデックス || 管理者へメール |