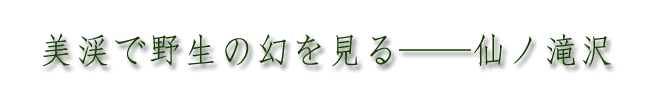

《8月9日》
未明に雷が鳴り、夜が明けるころから雨が降りだした。今日は雨のなかの滝登りかと、タープの庇から暗い空を見上げて憂鬱になるが、7時をすぎて撤収するころには、雨も上がってくれた。
出だしの2段15メートルの滝でさっそくザイルを出す。(081)下段は瀑流右に張り出した岩盤を登る。一カ所、身体が外へ押し出される感じで、ここはマントルぎみにずり上がる。下段と上段のあいだのテラスでピッチを切り、上段は逆に瀑水の左にルートを取る。落口近くで瀑芯をまたいで足をかけ、そのまま越える。
その上ですぐに3段30メートルの滝に出会う。下段は傾斜がきついが、トイ状の細い流水沿いがごつごつしていて登れそうだ。釜を胸まで浸かって着水点のすぐ右に取りつく。岩が脆く、浮き石を剥がしながら慎重に登る。(084)上の2段は容易だった。
これを越えると谷はひらけ、見上げると新潟と群馬の県境稜線がうっすらとガスをかぶっている。3メートルから10メートルくらいの滝がいくつも続き、水流と岩肌のはざまを探る四肢を中心にして、意識が研ぎすまされていく。そういえば、ここまで雪渓がまったくないのはちょっと意外だ。いくら今年が寡雪だったにしても、ブロックひとつ残っていないのも変な気がする。ひと月まえに、新潟地方でかなり激しい集中豪雨があったようだが、そのときにすべて圧し流されてしまったのだろうか。そのくらい強烈な濁流が谷を洗い流したのだとすると、岩魚の当たりがなくても致し方ないのかもしれない。連中も、本流のダム湖あたりまで一気に圧し流されてしまったのだろうか。(089)
正面に3段25メートルの滝が見えてくる。下から2段目まではナメ状で容易に登れそうだ。最上段がトイ状で一気に落ちているが、下からはちょっと様子がわからない。とにかく最上段の取りつきまで登ってみる。近づいてみると、先行の山田さんがさっそく左の側壁に取りついている。けっこう厳しそうだ。登るほどにスラブの一枚岩が立っており、山田さんの身体が中空に浮き上がったような恰好になってきて、下から見上げるこちらもはらはらしてくる。山田さんは持ち前の絶妙なバランスでなんとかここをもちこたえ、落口からまた細引きをたらしてもらう。(097)
いまのスリリングな綱渡りを見せられたあとでは、とても側壁に取りつく気にはなれず、トイ状の瀑芯には案外スタンスがあるだろうと勝手に想像して、水しぶきのなかに頭から突っ込んでいく。ところがさにあらず、しぶきの裏はつるつるでぬめっており、全身に瀑水を浴びたまま、固まってしまう。おまけに、かろうじて左足を置いていたスタンスが剥がれて、思わず細引きにテンションをかけてしまった。とにかくシャワーの苦しさから逃れようとだましだましはい上がり、ぜいぜい荒い息をつきながらなんとか落口へ抜けた。(100)ラストの高坂はどうやって登ってくるだろうかと上から見ていたが、側壁と瀑芯の中間あたりのラインを器用に拾いながら、水しぶきをかぶることもなくあっさりと抜けてきた。なんだ、そんな手があったのか。
ここを越えると二俣で、谷はいっそうひらけてくる。遡行図を確認して左俣の階段状のナメに向かう。(102)しだいに両岸からボサがかぶってきて、源流部に入ったことが知れる。だが、滝はまだまだ続く。「仙ノ滝沢」の名は、千の滝が転じたものではなかろうか。派手に大きな滝がないかわりに、5メートル前後の滝が源頭までえんえんと続く。
奥の二俣を左に入り、水の涸れかかった小滝を強引に腕力でよじ登ったりしているうちに、熊笹と小灌木の混じった密藪に突きあたる。30分ほど藪を漕ぎ、傾斜のきつい草原に出て、また熊笹の海を泳ぐと、笹におおわれた本谷山のピークに出た。ここもほとんど人の通った形跡のない、しぶいピークだ。対岸の越後沢左俣の源頭部は、びっしりと雪渓に埋まっている。
ガスで展望もきかないので、早々に下山にかかる。(118)小穂口ノ頭を越え、中尾ツルネに入ると、よく刈り込まれた尾根をまっすぐに下る。でもなぜだろう、稜線にいたる尾根道だけ整備して、肝心の稜線に道がないとは……。途中、ブナと五葉松の巨木がぴったりと合体して成長している珍しい光景に出会う。たがいの幹が半円形にがっちりと組みあって、ほとんど一本の木と化しており、接合部には指を入れる隙間もないほどだ。
内膳ノ落合で林道に下り立ち、ほっとしたのもつかのま、帰りもやはりアブの襲来を受ける。かたわらに三国川の、白い岩肌と蒼い淵が織りなす渓谷美を愛でながら、鼻歌まじりに歩いてみたいものだが、とてもそんな悠長なことは言ってられない。防虫ネットをかぶって終始うつむきながら、ひたすら小走りにアブを追いはらう。「駒子の湯」で汗を流し、そのあと大ジョッキで乾杯。充実した3日間が終わった。
仙ノ滝沢は、じつに密度の濃い沢だった。原生の香りをとどめひっそりとたたずむ端正な山襞の奥へ、じわじわと分け入っていく官能があった。秀麗な滝、緑濃い草付き、すっきりとせり上がっていく険谷――スケールや装飾による派手さはないものの、冗長なところ、大雑把なところがきれいにそぎ落とされ、緻密に、念入りに、いわば幾何学的に凝縮された美渓だった。そのなかを、岩の感触をたしかめ、瀑水に耳をすまし、ときにちぎれそうな草を掴んで夢中でよじ登っていくうちに、谷の肢体と自分の身体が皮膚をとおして呼応しあい、その境界を水が、記憶の底に流れる野生の源泉が、陽と風にさらされて行き過ぎる、そんな幻を見た夏の日だった。(016、086、104、120)