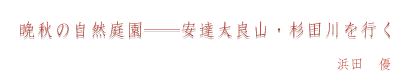
弐
遠藤ヶ滝を越えると、さっきの中年女性パーティが身支度をしていた。会釈をして通りすぎると、今度は右岸のやや離れたところに、初老の男性が三脚を立てて紅葉の渓谷を狙っていた。ここでも会釈だけして通りすぎる。これからさき、沢のなかで人に出会うことはなかった。
沢床はゴーロと言っても、よく磨かれた小さな石ばかりだ。そこに赤や茶の落ち葉が散り積もっている。両岸はゆったりとひらけていて、色づいた広葉樹が沢筋いっぱいに枝をひろげ、空を覆う。やがて小さなナメ滝があらわれはじめた。滝壺の釜には、へりまで流れに押された落ち葉が重なりあって、堰をつくっている。一枚一枚、縦に押しつけられた無数の落ち葉が、不思議な褶曲を描いて、層をなしている。それを踏みしだくと、やわらかい泥に足を取られるように、じわじわと水に浸かっていく。水に手を入れるとさすがに冷たいが、足は腿くらいまで浸かっても、さして冷たさは感じない。
やがて60メートルのナメに出会う。暗灰色の硬い岩畳の襞を、強すぎもせず、弱くもない水しぶきが洗っている。ここらあたりからやっと、胸のあたりの妙なざわめきが沈静してきた。流れの芯に足を踏み出すと、ふくらはぎあたりの感触が心地よい。自然と注意が足裏に集中するようになり、ナメ越えに没頭していた。
つづいて落差5メートルほどのナメ滝。ここは流れに磨かれた岩が赤い。右岸の階段状を登る。木々のあいだから射しこむ日ざしが、明るさを増してきた。それにつれて、木々の葉の色づきもあざやかさを増す。喬木の黄土色、低木の赤、斜面に近い緑と、色のうえに色を重ねて混ざりあっている。色の混ざりあった視界は、遠近感も混ざりあう。
8メートルの滝は大きな釜をしたがえている。釜は黒みがかった藍色で、底が見えない。へりの落ち葉の堰と岩のあいだを、そろりそろりと行く。踏み抜いて足を取られると、腰から上まで浸かりそうだから。滝には右岸から取りつく。岩は硬くほどよい突起で、あっけなく落口に立った。ただし、スタンスにも落ち葉が積もっているので滑りやすく、足を置くまえに落ち葉を払ってやる必要がある。
すぐ目の前に15メートルの滝が懸かっている。この沢でいちばん落差のある滝だ。この滝にも右岸から取りつく。四分の三くらい登ったところで、側壁の左手に三段の小さな梯子が懸けてある。たしかに、そのまま右へ落口に抜けようとすると、つるつるの岩のでっぱりが迫りだしていて、ちょっと手が出そうにない。しかたなく梯子のほうへ足が向くのだが、梯子じたいには手を掛けないで登ることができた。あとは右にトラバースして落口へ。この梯子はいささか興醒めだった。あるいはここで事故でもあったのかもしれない。
7メートルのトイ状、3メートルの赤茶けたナメと快適に越していくと、沢は水平にひらけて、その奥に美瀑が目に入ってきた。わくわくしながら近づいていく。
*

10m二条の滝
まずはこの光景をじっくりと瞼に焼きつけ、それからおもむろにルートを描きたい。そう思っても、足が自然に滝のほうに近づいてしまう。この滝には左岸から取りつき、登るにつれて水線に近づいていく。あと2メートルほどを残した上段のテラスで滝身に立ち、そこから二条の中間を二手で落口に立った。
この滝を越えると、両岸が少しせばまったようになる。そのなかをいくつものナメと釜がつづいている。小ぶりなナメにくらべて、釜はどれも意外に大きく、深い。朽葉と岩苔に守られた、青緑の静謐な淵だ。右から左から、釜のへりを滑らないように慎重にへつっていく。夏ならばじゃぶじゃぶと泳いで行くのがよいだろう。ナメ床は赤かったり黒かったり。5メートルほどの、若干大きめのナメ滝を左岸から越え、沢が右に湾曲したところで、水辺に憩っていた鳥が数羽、驚いていっせいに飛び立った。
ナメの連瀑を過ぎるとすぐ、ばったりと二俣に出会った。一気に前方の視界がひらける。右左どちらを向いても、流れはゆるやかな山稜のすそへと消えていく。時刻は11時25分。遠藤ヶ滝を発ってから2時間弱。なんだか夢中で歩いてきたようだ。
それにしても、なんて愛らしい二俣だろう。右俣は赤い川床、左俣は碧玉色の川床からほぼ等量の流れがやさしく寄り添い、浅い淵にすいこまれていく。そう、ちょうど右手と左手を、そっと重ねあわせたような風情だ。唐突なところ、出会いがしらの印象はまったくない。水と水は、はじめからここで出会うことを知っていたかのように、ひとつになって混じりあう。
この静けさ、このおだやかさは、いったい何だろう。
水音のかそけさと、日ざしのやわらかさに酔って、そう自分に問いかけてみる。この酔いは、たとえば上越のU字型にえぐれたスラブの底で、ザバザバと大きな沢音を聞いているうちに、やがて意識が身体の外に流れだし、意識のかわりに水が、ザバザバと音をたてて身体のなかを流れはじめるのを感じるような、ある種暴力的な酩酊感ではない。あれはどこか忘我の感覚に近い。
いまの酔いはなんというか、ずっと内省的なものだ。ここは、何かものの気配に満ちている。とはいえけっして生きもののそれではない。水が、岩が、落ち葉が、木々が、それぞれに息づいている。ひそひそと囁きあっている。その囁きあうさまざまな声が、あまりにも微妙に、あまりにも自然に響きあい、共鳴しているので、じっさいにはなにも聞こえないのだ。
わたしは耳を澄まし、もう一度自問してみる。この静けさ、このおだやかさは、いったい何だろう。
見上げるとブナの枝についた葉が、枝の末端は黄土色、中間は薄黄色、たもとは黄緑色と、グラデーションをなして絡まりあっている。わたしのすぐ近くで囁きあう水や岩や木の声が、わたしの身体に染みこみ、じわじわと浸透して、わたしのなかのさまざまな想念や気遣い、そのざわめきやその色どりと響きあい、共鳴したなら、わたしはきっと、この無音のさまざまな声を聞きわけることができるのだろう。



